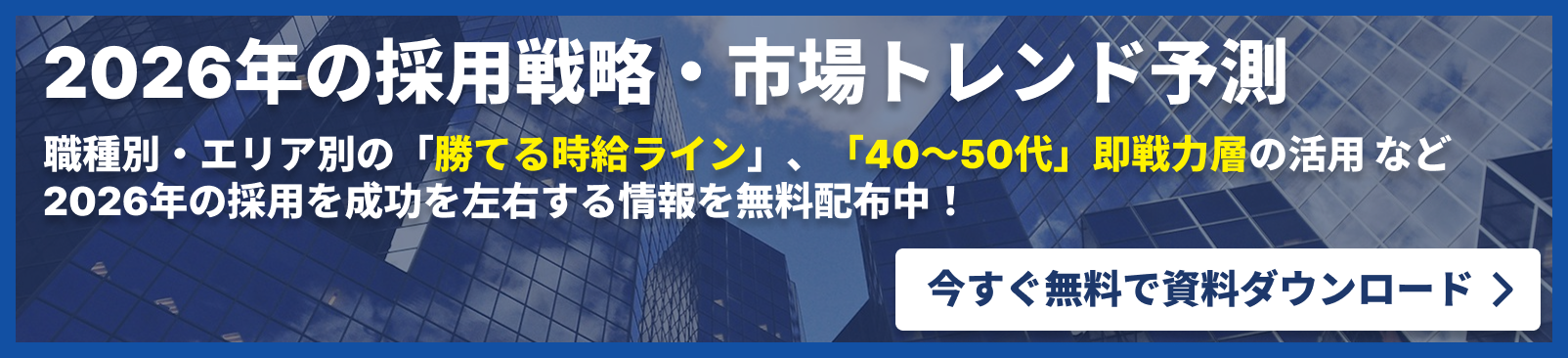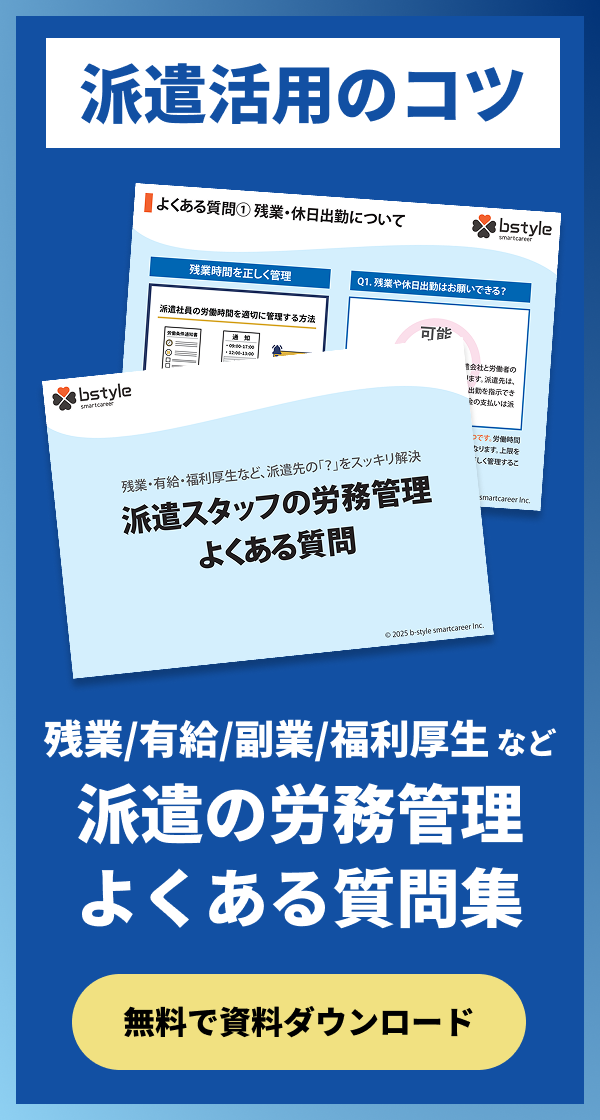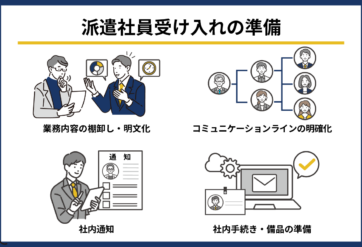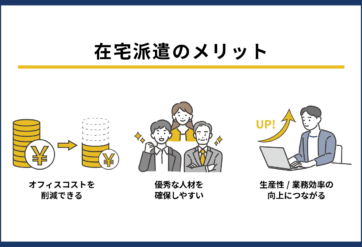- 人材派遣の基本
派遣社員の副業の取り扱いは?派遣先企業向けの注意点を解説
近年、働き方の多様化や収入アップを目指して、副業を始める人が増えています。しかし、派遣社員の副業については、「法的に問題ないのか?」「派遣先企業としてどう対応すべきか?」など、疑問や不安を抱えている企業担当者も多いでしょう。
派遣社員の副業は、基本的に派遣社員の雇用主である派遣会社の就業規則が適用されます。そのため、まずは派遣会社への確認が必要です。
本記事では、派遣社員の副業に関する基本的な考え方や、派遣先企業における注意点、副業に係る税金・社会保険について解説します。
【無料お役立ち資料】
副業のルールなど労務管理のギモンが一気に解決
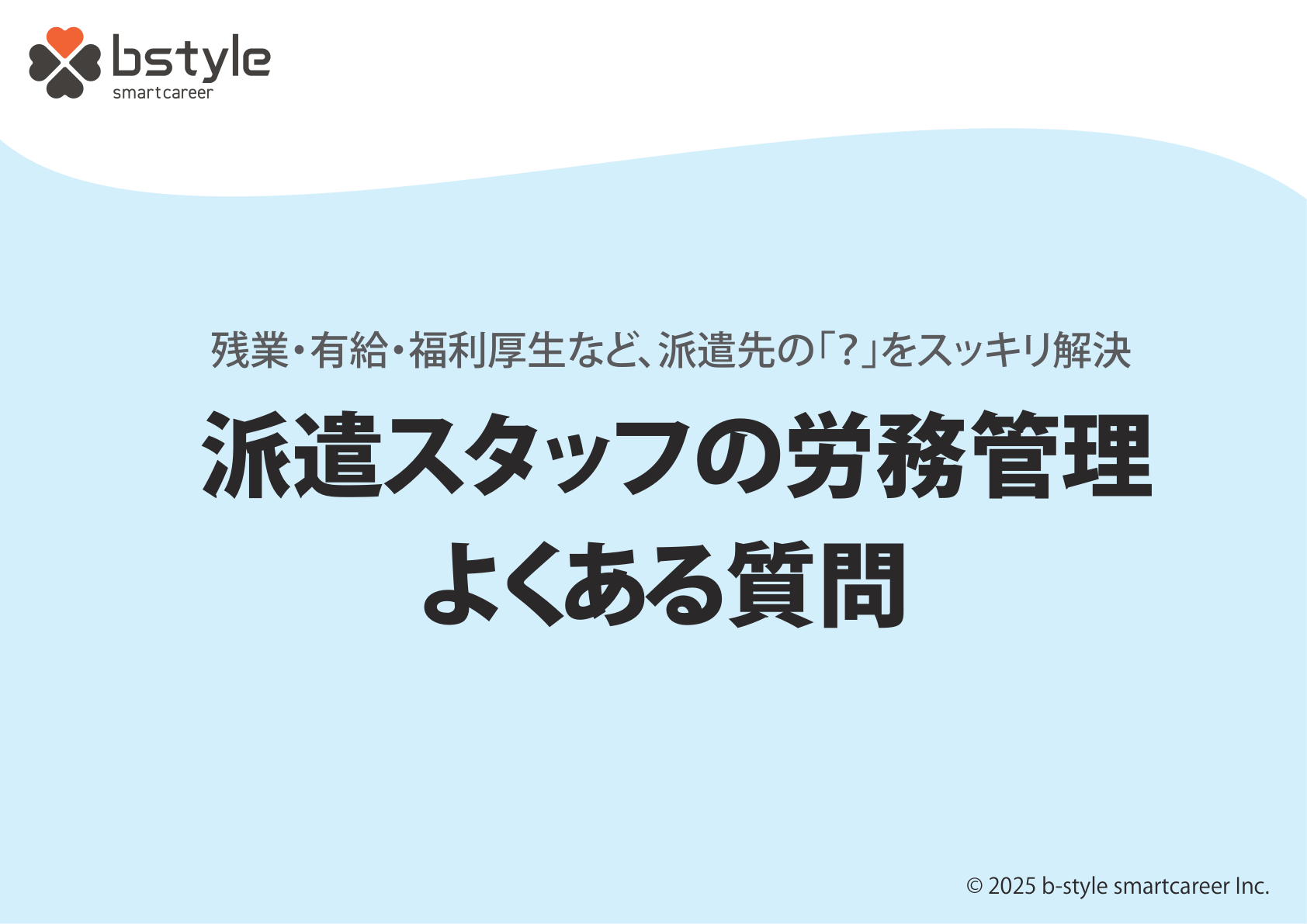
副業のルールを含めて、派遣人材の労務管理は正社員とは異なります。本資料では、「副業」「有給休暇」「残業」「福利厚生」に関するよくある質問にQ&A形式で回答、わかりやすく解説しています。
派遣社員の副業について調べている方におすすめです。
目次
派遣社員の副業に関する基本的な考え方
近年、政府は働き方改革の一環として、副業・兼業を推進しています。しかし、派遣社員の副業に関しては、派遣会社との契約関係により取り扱いが異なります。
対応方針を決めるために、まずは副業に関する考え方を理解しましょう。
国における副業の取り扱い
日本国憲法第22条では、職業選択の自由が保障されており、労働基準法でも副業を禁止する定めはありません。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
引用:衆議院『日本国憲法』
これまで、副業・兼業に関してはさまざまな裁判が行われてきました。それらの判例を踏まえ、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」において、労働者が労働時間以外の時間をどう利用するかは基本的には労働者の自由であり、原則として副業・兼業を認める方向で検討することが適当との見解を示しています。
ただし、企業が副業を制限することが許されるケースも存在します。具体的には、以下のような場合です。
- 労務提供上の支障となる場合
- 企業秘密が漏洩する場合
- 企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
- 競業により企業の利益を害する場合
これらのケースに該当しない限り、国としては副業を推進する立場を取っています。
適用されるのは原則、派遣会社の就業規則
派遣社員の副業に関しては、原則として雇用主である派遣会社の就業規則が適用されます。派遣会社によって、副業の可否や許可される条件は異なります。
一方、派遣会社が副業を認めていても、派遣先企業では副業を禁止している、あるいは特定の条件下でのみ認めているなどの場合もあるでしょう。このような場合、トラブルにつながらないよう、派遣会社と派遣先企業で話し合い、取り決めをしておくことが重要です。
仮に、派遣会社と派遣先企業で締結される労働者派遣契約において「派遣社員は派遣先企業の就業規則に従う」という旨の合意がなされていた場合、派遣社員は派遣会社との労働契約に合意したうえで、派遣先企業の就業規則に従うことになります。
派遣社員の副業における派遣先企業の注意点
派遣社員が副業を行う場合、派遣先企業は就業規則への記載や情報漏洩リスクへの対応など、いくつかの重要な点に注意を払う必要があります。
これらの注意点を事前に把握して適切な対策を講じると、トラブルを未然に防ぎつつ、派遣社員と良好な関係を築けるでしょう。
派遣会社と副業に関して取り決めて就業規則に記載しておく
派遣社員の副業に関して、派遣先企業と派遣会社の間で事前に明確な取り決めをしておくと、トラブルを避けやすくなります。その合意内容に基づき、副業に関するルールを自社(派遣先企業)の就業規則に定めておくとよいでしょう。
また、派遣会社にも合意内容を就業規則へ反映するよう依頼することが重要です。
厚生労働省が公表しているモデル就業規則には、副業・兼業に関する規定例が示されています。
(副業・兼業)
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
引用:厚生労働省『副業・兼業の促進に関するガイドライン』
ただし、これはあくまで一例であり、必ずしもこの規定例通りにする必要はありません。
副業を認める範囲や条件、届出の方法など、具体的な内容は派遣会社と十分に協議し、双方の合意のもとで決定することが望ましいでしょう。
派遣社員の労働時間管理と健康管理を徹底する
派遣社員が副業を行う場合、派遣先企業による労働時間管理と健康管理の徹底が不可欠です。
労働基準法では、企業に雇用される形態で副業・兼業を行う場合、本業と副業の労働時間を通算するよう定められています。
派遣社員の就業時間が副業と合わせて週40時間または1日8時間を超える場合は、派遣会社が36(サブロク)協定を締結・届出していなければなりません。
36協定とは、法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせる際に、派遣会社と派遣社員の間で締結される協定です。派遣会社が締結した月45時間、年360時間(1日目安2時間程度)を上限とした残業時間の範囲内で、副業も行われることになります。
派遣先企業は、派遣会社が締結した36協定の時間内で収まるよう、労働時間を管理しなければいけません。
また、厚生労働省は、副業による過労が本業に影響しないよう、企業による確認を推奨しています。派遣先企業においても、定期的な健康状態の確認や相談窓口の設置など、派遣社員の心身の不調を早期に把握できる体制づくりが必要です。
派遣社員の残業に関しては、以下の記事も参考にしてください。
情報漏洩リスクへの対応策を定めておく
派遣社員が副業を行う際には、本業で得た機密情報や顧客データなどが意図せず外部に漏れるリスクが考えられます。派遣先企業は、このような情報漏洩を防ぐために、具体的な対策を講じる必要があります。
考えられる対応策は、以下のとおりです。
| 対応策 | 詳細 |
| 情報管理ポリシーの明確化 | ・派遣会社との契約時に情報管理に関する取り決めを明文化 ・派遣社員向けの情報セキュリティ研修を定期的に実施 |
| アクセス制限の設定 | ・業務上必要な情報のみにアクセス権限を限定 ・重要情報の持ち出し禁止ルールを徹底 |
| 派遣会社の副業届出制度についての把握 | ・派遣社員に副業の内容を派遣会社へ事前に申告してもらい、競合他社での就業などリスクの高いケースを把握してもらう ・副業内容によっては派遣会社に派遣先企業への共有を依頼し、情報隔離のための追加対策を検討してもらう |
適切な対策を講じると、派遣社員の副業にともなう情報漏洩リスクを低減し、企業の機密情報を保護しやすくなります。
派遣社員の副業と税金・社会保険について
派遣社員が副業を行う場合、税金や社会保険の手続きは派遣社員自身と派遣会社が対応します。
とはいえ、派遣先企業も基本的な知識をもっておくと、問い合わせ対応やトラブル防止に役立ちます。税金・社会保険の知識を押さえておきましょう。
確定申告の必要条件
副業による所得(収入から必要経費を差し引いた金額)の合計が年間で20万円を超える場合、原則として個人による確定申告が必要です。
一方、この所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、確定申告が不要な場合でも、住民税は所得額に応じて支払わなければならないため、住民税に関しての申告は必要になります。
確定申告や住民税の申告を怠ると、延滞税や加算税が課される可能性があります。派遣社員から問い合わせがあったときには、必ず手続きを行うよう伝えるとよいでしょう。
社会保険・雇用保険への影響
派遣社員の副業も例外なく、就業時間などによって社会保険や雇用保険の取り扱いに影響を与える可能性があります。
雇用保険は、1週間の所定労働時間が、20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合に原則加入となります。
ただし、雇用保険は「主たる賃金」を受ける会社で加入するため、本業の派遣会社ですでに加入していれば、副業先で二重に加入する必要はありません。
一方、社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、副業によって適用状況が変わる可能性があります。特に以下の条件をすべて満たす場合、副業先でも社会保険への加入が必要です。
- 1週間の就業時間が20時間以上
- 月額の給与が88,000円以上(残業代や通勤手当などは含まない)
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
- 学生ではない
- 副業先における厚生年金保険の被保険者数が51人以上
雇用保険・社会保険の加入手続きや保険料の納付義務は派遣会社が負いますが、派遣先企業は派遣社員の実際の労働時間や就業状況を正確に把握する立場にあります。
派遣社員の健康管理や法令遵守の観点からも、副業による労働時間の増加などの情報は、派遣会社と適切に共有することが重要です。
派遣社員の副業に関してよくある質問
派遣社員の副業に関しては、さまざまな疑問が聞かれます。よく寄せられる質問とその回答をまとめましたので、疑問の解消にお役立てください。
派遣社員は副業してもよいのでしょうか?
派遣社員の副業は、法律上は基本的に認められています。
ただし、派遣社員は原則、派遣会社の就業規則に従うため、派遣会社によっては禁止される場合もあります。どのように取り扱うかは、派遣会社に確認しましょう。
派遣先企業と派遣会社で副業の方針が異なる場合はどうなりますか?
原則、派遣会社の就業規則が適用されます。
あらかじめ派遣先企業と派遣会社の間で副業に関して取り決めておくと、トラブルにつながりづらくなります。
まとめ
副業に関して、厚生労働省では労働者が労働時間以外の時間をどう利用するかは、基本的には労働者の自由であり、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当とされています。
ただし、派遣社員の副業については、基本的に派遣社員の雇用主である派遣会社の就業規則が適用されます。
派遣会社によっても副業が許可されているかどうかは方針が異なるため、まずは派遣会社に確認が必要です。
派遣先企業としては、副業に関してあらかじめ派遣会社と取り決めを行い、就業規則に記載しておくとよいでしょう。
また、派遣社員が心身の不調を訴えやすい環境を整える、情報漏洩リスクへの対応策を定めておくなどの取り組みも求められます。
トラブルにつながらないよう、派遣会社と密に連携しておくことが重要です。
【無料お役立ち資料】
副業のルールなど労務管理のギモンが一気に解決
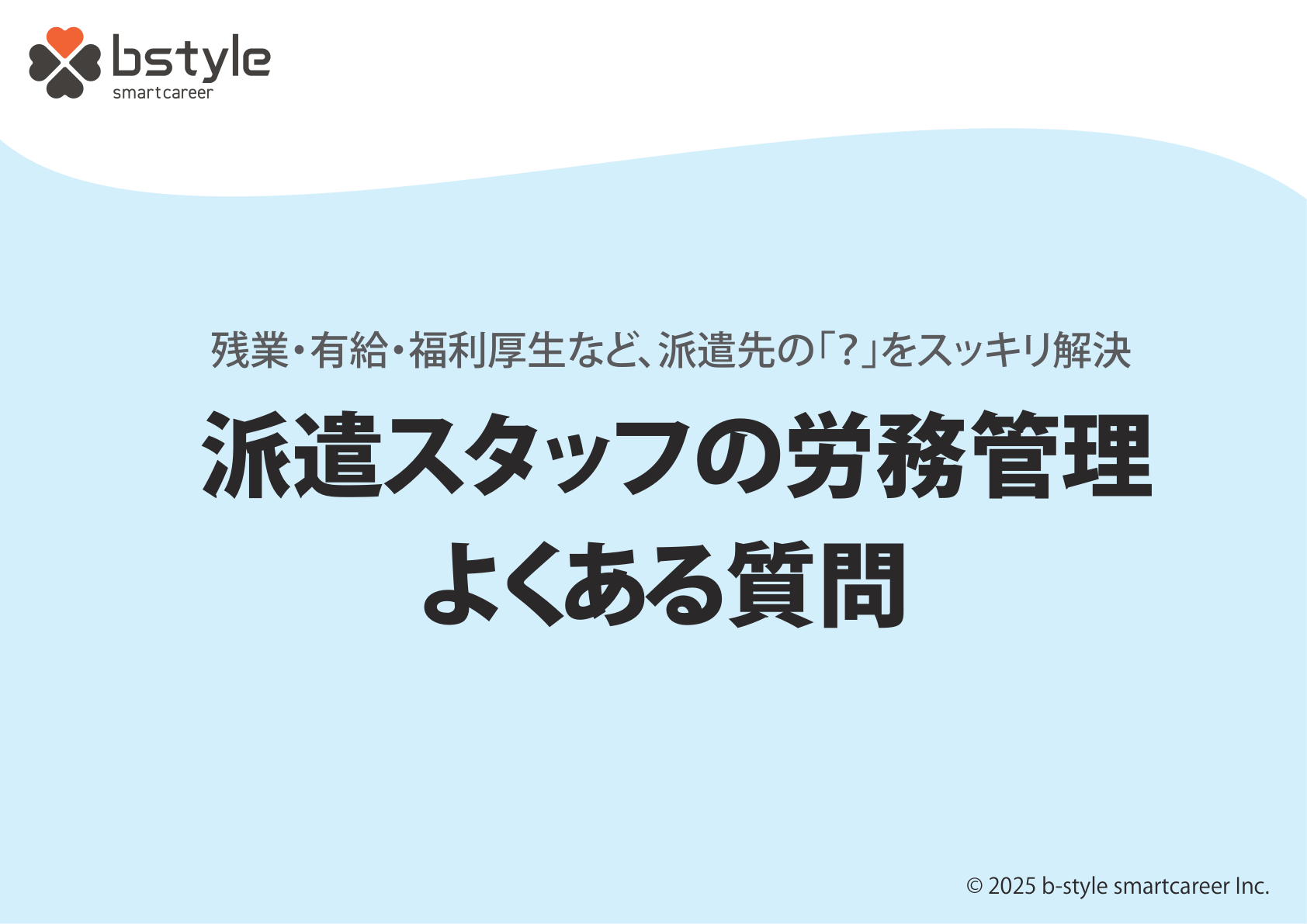
副業のルールを含めて、派遣人材の労務管理は正社員とは異なります。本資料では、「副業」「有給休暇」「残業」「福利厚生」に関するよくある質問にQ&A形式で回答、わかりやすく解説しています。
派遣社員の副業について調べている方におすすめです。